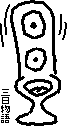
2010 N 2 21 ɏ ߂ 200km ̃u x ɎQ B u x o N B ͂ 茾 Čo B ꉞ Ƃ͂ A g ̊ 6 2 s ( F 200km,300km,400kmx2,600kmx2 / r ^ C F 400km,600km ) 킯 ŁA Ȃ ƂȂ K v ȃ m A s v Ȃ ̂Ȃǂ 킩 悤 ɂȂ B o ɗL p Ƃ A s v Ƃ q ׂ B ɂȂ o ̌o ܂Ƃ ^ u u x Ƀ` W 2010 v ̎ ɃO _ O _ Əq ׂĂ B Q l ɂȂ郂 m Ɗ肤 B
܂ A ڂ l i Ȃǂ Q l ɂȂ 悤 ɂȂ ׂ amazon ւ̃ N Ă B ߏ ̎ ] ԉ ōw Ăق A ɂ X Ȃ Ȃ ʔ̂ōw ̂ A B
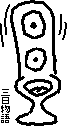
܂ A e ڂɂ ĕi \ Œ A ꂼ ɂ Ă͂ ɏڂ L q ɂ Ă͕ i ȂǃV F A ł \ ̂ 邩 A ̏ Ȃǂō Ƃ ɂ͐ Ă 炦 ΒT Ă݂邱 Ƃ ł ̂Ń V N B
i N h ̂ŁA ǂ ǂƒ 炵 Ă 肵 āA ܂ʁB A Ă ̂ɏ ĂȂ Ȃ H Ƃ A R ̑ ͂ǂ ȂH Ƃ 玿 ₵ Ă Ώ Č m ʁB
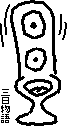
\ Ȃ K { ɂ Ă̓V F A ł ̂͑ Ȃ B
| i | V F A | |||
|---|---|---|---|---|
| ] | V N N X | ̂ CX900 Ȃ b ɂȂ | | | S 18kg | ~ |
| O Ɠ | 400km ȏ ł͓K v | GENTOS X [ p [ t @ C AXX SF-333XX | FENIX LD20 | K { | ~ | |
| 납 猩 Ԃ v | K { | ݒu | ~ | |
| ˃x X g ˂ ˌ | x g | Ƃ炳 ꂽ Ƃ Ɍ 悤 ɂ | K { | w | ~ |
| w b g | g p Ă ̂ K X | K { | ~ | |
| x | ` [ I Ė A | K { | ݒu | ~ |
| C | 悤 SH-M076 𗚂 Ă | K { | g p h K v | ~ |

d ʂ 12kg Ƃ Ȃ d ̂ŁA ܂肨 ߂͂ł Ȃ A ͂ ̈ Œʋ u x V N N X [ X I [ v X g [ g } b v GPS O Ȃ B
^ C (700x32C) Ƃ͂ Ƃƈ Ƃ B ق ́A ^ C ׂ ق J b R ȉ l ς̒ ƃJ b R ƂƁA I Ȗʂő s R( C R H ʒ R Ȃ ) 傫 B c ƃ` [ u 傫 ̂Ńu x ̎ ɂ͂ Ȃ ɉו ɂȂ B
ق ́A Ԃ Ƃ ^ C Ȃ Ȃ A p N m 炸 B čŏ ̂ ͏ S n d ŋ C ߂ɂ Ă 烊 ł p N B ̌ ^ C ̋K i ς ܂ŋ C 邱 Ƃɂ ď S n ߂ A ̌ ͈ p N Ȃ B ŘH ʂɂ ܂ C g 킸 ǂ ɂł ˌ Ă B u x ł͊ { I ɕܑ H Ȃ̂ł ܂ C ɂ K v ͂Ȃ A i Ă Ƃ ɓˑR ̍ 낪 Ă Ă A K c Ƃ āu I r b N ȁ` v ōςB
d ʂɊւ ẮA ^ C ̊W 邩 Ȃ A y InterMax (8kg) 肽 A ꂪ ͂ [ ̂Ȃ ̂ āA ʏ푖 s ł X s [ h ꊄ 炢 B InterMax ŁA g ̏ ̊ ɂ Ă Ƃ ő 肵 B CX900 ł 18 ` 19 邪 A InterMax 16 ` 17 ł ς ꊄ ȏ㑁 Ȃ I ܂ A y ^ C ȊO ɁA ] Ԃ̐v 쓮 n ̗ǂ ( CX900 Sora ŁA InterMax DuraAce ) Ȃǂ ׂĂɍō Ȏ ] Ԃ̗ǂ Ń^ C ꊄ ȏ㑁 ̂ Όy ] Ԃ ق Ȃ Ȃ B
^ C Ƃ A t g g v Ƃ ̂ C ǂ܂ ɍs A( K o c) [ h ̐l ɕt Ă 邱 Ƃ B ꉞ c [ O Ƃ K s ݂ Ȃ̏C s Ɗ Ă ƂŁA f Ȃ x ɗ͂ Ίy ނ Ƃ ł Ǝv B Ƀ^ C ̂ŃJ [ u ȂǂŌ E Ƃ ̋ ́A ׂ ^ C ɂ₩ Ǝv B X ւ Ă ȁ[ Ǝv Ƃ 邪 A ` Ċ Ńc Ɨ 銴 ͏ Ȃ B
^ C ̑ ̓} } ` ɂ ʂ ̂ŁA ʋɂ ̂܂g ĉ Ђ̎ ] Ԓu ɂ u y s @ Ă 钆 ɍׂ ^ C ̐퓬 @ v ݂ Ɍ Ȃ Ƃ ͈ S ł B
u x ̑ ̃y C W ŏ ̂ A A ^ C ̔ Ƃ ^ C ̂ ̂Ƃ V N N X p ̃^ C ɕς ̂܂܃V N N X [ X ɏo 邼 ͂ Ƃ (^^; U
ʐ^ ł͐^ ̗\ ĎO { 邪 A ^ ɂ Ă͉ Ȃ B { Ԃł̓n h ɂ͑O Ɠ { B { Ƃ ɈÂ Ȃ ꂽ 肷 邱 Ƃ͂Ȃ B d r ̓ j O R X g Ɠ 萫 l ƒP O(AA) d r ł 낦 ق 낤 B ̓ j O R X g } 邽 ߂ɃG l [ v g p( q) B d r ̃ ` Ƃ Ē ŁA Ɩ 邢 ʏ g 130 [ m(AAx3 ʐ^ ł͎ O ) g A Β[ ɂ͍ŋ 邢 A d r ̃ ` 1 Ԓ x ҂ł Ȃ 180 [ m(AAx2 ʐ^ ł͉ ) B X 130 [ m ōς܂ 邱 Ƃ ł B X ̂Ȃ ^ Âȓ Ƃ 130 [ m ɉ 180 [ m _ B

܂ 130 [ m ̐ B GENTOS( W F g X) X [ p [ t @ C AXX SF-333XX Ƃ m ŁA i r I ɖ 邭 āA d r ̃ ` ǂ B _ ͒ ƁB q ֗ z _ [ Q K v ȗ R ɂ 邪 A ̂Ńn h Ɉ ӏ ߂Őݒu Əd S ̊W ɂ o 킯 B G ɂ ȁB Ȃ ĒP O d r O { (AAx3) u v ɐs B A ̓ ̒ ǂ ɂ Δ r I 邭 ē_ Ԃ ̂ŏ p ł Ǝv B ےʋɂ͂ ̑O Ɠ g Ă B


180 [ m ̐ B FENIX LD20 Ƃ d ŁA Ƃɂ 邢 ƁA P O d r { Ńo X ꂽ ` Ă B _ ͓d r ̃ ` Z ƁB Ȃ A Ɩ 邢 uEagleTac P20A2 MarkII v ̂悤 Ȑ i 邩 炻 I ق Ȃ B ҂ɋ ʂ ̂́A 邢 _ Ԃ͒Z Ƃ B ܂ A O ̂ ƂȂ c
g Ƃ ẮA X ͏ p C g ő Ă Ă A т̒ Ȃǂ͈Â Đ悪 ʂ Ȃ Ƃ ɓ_ Ԃ Z Ă 邢 C g Ǝ˂ 킯 B Ԃ̒ ɂ Ƃ Ɍ 납 疾 邢 C g Ă f 낤 A Ƃ ɂ 邢 ق ͏ ق Ǝv B

{ ͒P O { Ȃ { g ^ C v ق A P l { g ^ C v Ȃ B ܂ A قǂłȂ 100 Ԃ 炢 炵 ̂ō Ƃ͂Ȃ B G l [ v g Ă ̂Ńu x O ɂ͏[ d đ Ă B ʂ̈ꎟ d r( [ d ł Ȃ ^ C v) ȒP l d r ł ̂ A I Ɏ Ă P l d r G l [ v Ȃ̂ł ̂܂܉^ p Ă B
i ͓ { E ̎ʐ^ ̂悤 ɃN X | Ă B { ͋ߏ DIY ̂ X Ŕ Ă m ōŒ 炪 ̂ɂ | 悤 ɒ p Ă B { ɂ āA ͎l { ̃} W b N e [ v ^ ̔ ˃x g( _ C \ [ œ Z b g w 悤 ȋC ) A 瓷 ̂ɂ | ł 钷 ɂȂ ̂ŁA N X | ̂ ɂ Ă B
l { ̃} W b N e [ v ^ ̔ ˃x g ͂ Ƃ Ύ ⑫ Ȃǂ Œ肵 Ƃ ȂǂɎg Ƃ B h p ɉ g p b P 𒅗p 邱 Ƃ 邪 ` F [ Ɋ ܂ Ȃ 悤 ɂ ̃} W b N e [ v x g g p Ȃǂ̗p r B N X | Ă ƌ ڂ A Ԃ̓N } Ɏ F Ă 炤 ߂ɂ͖ڗ ĂΏ B

̎ʐ^ ł̓~ [ ȕ i t Ă 邪 ͂͂ Ă B m [ ~ \ ی삷 邽 ߂ɂ̓w b g K v B W ̓w b g ꂽ ق ̐l ɂƂ Ă͂ K x Ǝv B A K { 瓪 Ƀt B b g ̂ Ԃ낤 B

` [ ƂȂ A B قƂ ǖ炵 Ƃ͂Ȃ A y 蓹 ȂǂŃR h ӂ Ă Ƃ ɂ͉ ӎ Ɍ Ă 炤 Ŗ炷 Ƃ B l ͋} ȓ ͂ ܂ Ȃ ǁA R h ͓ˑR ͂˂ 悤 Ɍ ĂȂ ق ֈړ 邱 Ƃ 邩 A ݂ ̕s K 邽 ߂ɂ ӎ Ă 炢 B R e ʂ Ƃ ͂ 肾 B Њd 邽 ߂̌x J ł͂Ȃ ̂ A s ҂Ɂu h P I v Ƃ 悤 Ȗ炵 ͂ Ȃ 悤 ɂ 悤 B
镽 y _ Ƃ N [ g ̌C Ŏ ] Ԃɏ ̂ Ȃ A y _ ɑ A ƃ N B y _ ނ łȂ A y _ A ɏR A G グ A O ɏR o Ƃ t 邱 Ƃ ł ̂ŁA y _ ɗ͂ Ă 鎞 Ԃ Ȃ g [ ^ Ƃ ă N ɂȂ鐡 @ B ł̓M A i 炢 ς 悤 Ɏv A ꂭ 炢 N ɂȂ ̂ B m ɏ n ߂ƒ ~ ̂Ƃ ɁA y _ Ƒ A 铮 A ɂ͂ 삪 K v ŗ K K v A Ƃ Ȃ ̂ B


A ʂ̌C ł 邱 Ƃ 邱 Ƃ l Ȃ痼 ʘA ł͂Ȃ A Жʂ A ^ C v ̃y _ ( ̍ ̃^ C v) g ƂŁA p ł 邵 A ŋ߂܂Ŏg p Ă B y _ A 悤 ɂȂ Ƒ̊ I ɁA A Ȃ ʂ̃y _ ͂ƂĂ ɂ Ȃ Ă ܂ A ʂ̌C ł͏ Ȃ Ȃ邱 Ƃ ܂ ė ʘA ^ C v( ̉E ̃^ C v) ̃y _ ɕς Ă ܂ A ߓn ͕Жʕ y _ E ЖʘA ^ C v ͂ I Ǝv B
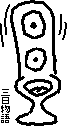
̍ ł͂ Ε֗ Ǝv m グ B Ȃ Ă Ƃ Ȃ邪 A ƕ֗ ȃ m B
m ɂ Ă̓V F A ł ̂Ŗ Ȃǂ̂Ƃ ŕK v ȂƂ ɂ́A \ ̂Ƃ ɂ͑ k ɂ̂ 邩 Ȃ B
| i | V F A | |||
|---|---|---|---|---|
| w b g p | w b g ɂ Ԃ v | better | ||
| C | t ` o u p | Έ S | ||
| ` [ u | ̏ꍇ 700x32c x2 | Έ S | ||
| p N C L b g | p N C 邽 ߂̃p b ` E ڒ ܁E ₷ | Έ S | g p | |
| [ ^ [ | ̂葪 | K { | ~ | |
| GPS | ̏ꍇ Colorado 300 | better | ~ | |
| d r | P O eneloop 𑽗p | K { | w | |
| w b f | ɂ w b h C g | 300km ȏ ŕK v | g p | |
| ܂ d ɂ ܂ g p | K { | g p | ||
| E B h u [ J | Ɨp ̃ b P | K { | g p | |
| C J o [ | Ă ܂ | ɂ͎ K { | g p | ~ |
| ֍s | d ԓ ɏ Ƃ Ɏ ] Ԃ | 400km ȏ㎝ Q \ | g p | |
| T O X | ̏ꍇ ͖ F ̃T O X | ɂ͎ K { | g p | ~ |
| o b N ~ [ | n h G h ɂ 鋾 | Έ S | ~ | |
| g b v ` [ u ̃ m | g b v ` [ u ɂ 鏬 | Ε֗ | ~ | |
| ֗ z _ [ | C g [ ^ [ ̑ | ɂ͎ K { | ~ | |
| R } } X N [ | R } } ₷ 鑕 u | ɂ͎ K { | ~ |
Ԃ̑ s Ƀg l ɓ Ƃ ɂ͔ _ B C x ߂ Ȃ A Ԃ 猩 Ă 炦 邩 Ȃ B ԑ̂ɂ Ă K { ̂ق ͑ s ɃX C b ` G 邱 Ƃ ł Ȃ ̂Ŕ ͋C y ɓ_ ɂ B w b g ɂ Ă Ȃ 㓪 ƐG ̂œ_ ₷ B d ʂ ƂȂ A Ă ăo ` ͂ Ȃ 낤 B S ̂ ߂Ƃ Ă ߌ ł͂Ȃ A ق ̃u x C _ [ Ă ƌ ₷ ̂Ŏ Ԃ 悭 ƐM B
͂܂ u x ł̃p N ̌o Ȃ B A Ȃ Ƃ͌ Ȃ B l Ǝ Ă Ȃ 킯 ɂ͂ Ȃ B Ƃ ƂŁA p N ̂ ߂Ɏ Q Ă B
^ C ` [ u ͕K Ă B Ȃ A 700x32C Ȃ A ȑ ^ C ̎ ] Ԃɏ Ă q g ͌ Ƃ Ȃ ̂ŁA V F A ł Ƃ A @ ͂Ȃ 낤 ȂƎv Ă B a Ԃɏ Ă q g ƂȂ낤 B 700x23C ̃^ C ` [ u ͑ Ϗ ̂Ŏ čs Ȃ R ͂Ȃ Ǝv B( Ƃ 32C ̃^ C ` [ u 傫 Ǝv )
p N C L b g K Ă B 傫 ł d ł Ȃ ̂ň S Ǝ ۂ̃p N Ƃ ̂ ߂ɂ͕K { Ǝv B ߏ ̎ ] ԉ ōw Ă z ł Ȃ ̂ŁA ̂ łɍw Ă Ƃ 낤 B

K { Ǝv B L [ V [ g ȂǂŁA ڈ L q Ă 邪 A ̖ڈ ܂ʼn L [ g ł 邩 m 傫 ȏ B Ȃ A ̌o ͗L ̂ق M A l i ̂ŁA ߂ B ͗ R ͂킩 Ȃ ~ [ ȓ 邱 Ƃ B P C f X( y _ ̉ ] ) ƃL ` ̖ʂŊ ꂾ Ȃ̂ŁA @ \ Ƃ Ăق ǂ ͕ʓr l Ă悢 Ǝv B ꉞ u x ł͓ ̂肪 m ɑ Ŏ B
͉ ʂ̑傫 GARMIN Colorado 300 Ƃ GPS [ g p Ă 邪 A d r o J A d Ȃǂ̗ R 炠 ܂莩 ] ԗp ɂ͂ ߂ł Ȃ B A ق ̃q g g Ă ȂǏ ʂ l GARMIN Ђ GPS [ ͈ Ȃ I B ق ɂ Č ₷ A @ \ GPS [ ̂Ŏg Ă݂ Ɩʔ 낤 B
͊ { I ɂ̓R } }( L [ V [ g) Ɏg Ă āA GPS [ C Ɏg Ă q g B ɂƂ Ă GPS [ ́A Q l ɂƎg Ă x ŗ 肫 邱 Ƃ͂ Ă Ȃ B Ζ{ ɖ𗧂 ɂȂ Ă͂Ȃ Ȃ Ƃ u ƌ قǂł Ȃ B
d r ͑O Ɠ GPS [ Ȃǂɍŏ ɓ Ďg p A r Ō Ȃ ̂ Ƃ ] ܂ B A r œd r ͂ Ō \ s ւ B ͓ 萫 ƃ j O R X g A AA T C Y P O d r C Ɏg p Ă B ܂ A g 疈 x w Ȃ ͊ Ȃ ̂œd r( [ d ł d r) eneloop C Ɏg p Ă B d r( [ d ł d r) ̑ ɂ̓T [ h A p i \ j b N h A \ j [ h ȂNJe h Ǝv ̂ł D ȃ^ C v Ƃ Ǝv B

ق ̓d r Ȃ A eneloop ͈ꎟ d r( [ d ł Ȃ d r) Ɣ r Ƒ Ϗd ̂ŁA \ Q Ƃ ɂ͂ ̕ӂ l Ă B ܂ A w b f ɂ eneloop łȂ͂ ꎟ d r g p 邱 Ƃɂ Ă 邪 A R eneloop ɑ ̂Ńw b f ̓d r P [ X ɓ ƁA ɂȂ Ȃ o Ȃ ߗ l Ĉꎟ d r g p 邱 Ƃɂ Ă B
w b f ͖ 邳 A P O h A P l h ȂǍD ݂ɉ Ďg p Ƃ Ǝv B ͒P O h Ȃ̂ŁA P O g ^ C v ɂ Ă 邪 A eneloop Ɠd r ɓ V ̂Ńw b f ͗ O I Ɉꎟ d r( [ d ł Ȃ d r) g p Ă B ̎ Ȏg p ړI ́A Ԃɂ W ̊m F E n h ɂ R } } [ ^ ̐ ǂ݂̂ ߂̖ 肾 B ܂薾 邢 ƃn h ̂ ̂ ݂ Ɩڂ ނ̂ł łȂ Ă 悤 ȋC B A W ͂ 茩 ̂Ŗ 邢 ق 낤 o X Ǝv B

Ƃ ʼn Ńw b f Ƃ ̂ H c ^ ₪ 킭 A 炾 Ƃ Ȃ B w b h ̓d w b f Ƃ͕ Ƃ 邪 A ɋ Ă ꂽ l m Ȃ B
ŏ ͐ p ̎ ܂ g ( ʐ^ CHIBA ̂ ) A s Č ǎg Ȃ Ȃ B ́A w ܂ŕ ^ C v Ŏ ̂Ђ ɃN b V Ƃ ͂ƂĂ 悩 A ̍b ď Ƃ _ B ŏI I ɂ͍ Ɨp ( ̍b ̓W [ W [ n) ɉE ̑傫 ߂̎ ܂ J o [ Ƃ Ďg p 悤 ɂȂ B 傫 ڂ̎ ܂ d ˂Ă āA Ȃ 傫 ߂̎ ܂ Ƃ č Ɨp ܂݂̂Ƃ @ Ƃ B ] ԗp Ńs Ɨ ̂ ܂ Ȃ ̂ŁA ו ɂ͂Ȃ邪 w 悪 ₦ 铖 ɂ͍ ̂Ƃ ŗǂ B A w ܂ŕ ^ C v Ŏ ̂Ђ ɃN b V āA ̍b W [ W [ n ̎ ] ԗp ܂ [ q B

͎ ] ԗp ̃E B h u [ J ł͂Ȃ A J C Y z [ ̃ b P p Ă B 㔼 g A g ꂼ 298 ~ ƌ ŁA h \ ͏\ B ߋ ̃u x ŒE ŃL A ɂ Ă Ƃ ɂȂ Ƃ 邪 A l i l ƂȂ Ă ܂ R R t g R ɂ܂Ȃ ̂ ő ̗ _ B ǂ A J ~ A O ͂т т ŁA Œ ͔G ̂ 낤 { i I ȃJ b p b P ōς܂ Ă B ܂ A F ƊO ς u ݂ v Ɨ ₩ 邪 A C ͂ Ă i D 悭 Ă ̂Łu J b R H v Ƃ Ƃɂ Ă B DIY ̂ X A ދ X A 邢 ͍ ƒ Ă X ȂǂŒT Ă݂ Ƃ ̂ 邩 Ȃ B _ A ̂ɂ҂ 肵 ̂̂ق C R A ] ԗp Ɣ ̂ŏ Ȃ邩 A t g R ɗ] T p i ق Ǝv B ܁A ̓ [ h ] ԂłȂ A V N N X Ȏ ] Ԃ 玩 ] Ԑ p łȂ m g ̂ I V (
͏ ̍ ̃^ C v g Ă B ₽ ē 肻 ̂ ԃ} V ɂȂ B 5 ԂقǏ ăV P ł Ă ܂ قǂɓ ɂƂ Ă̖h \ Ƃ ẮA ܂ s \ V P ̎ łǂ ɂ Ȃ Ȃ B ꉞ C ƃJ o [ ̊ԂɎg ̂ăJ C ͂ ł݂ Ƃ 邪 A ܂ Ȃ B A M ͂ ނ Ƃ ł Ƃ b g ̂ŃJ o [ ͍ g p 肾 B
Ƃ o _ Ƃ ɂ͐ b ɂȂ邩 Ȃ A o _ ܂Ŏ ł Ă A ς胊 ^ C (DNF: Do Not Finish) Ƃ ͓d ԂŋA 킯 ŁA Ƃ B ֍s ܂̈Ӌ` ͂ق ̏ q ̈ߕ A j A v ɚʑ Ȃ ߂ɂ B \ ɕی ł Ă Ȃ S ~ ܗ֍s A Ƃ͎v A p ̃ m ق 䂾 Ǝv B m 荇 u Ƃ ̐Q ܂ɂ Ȃ邼 v Ƌ A ܂ @ Ȃ ̂ŗ֍s ܂Ƃ Ă݂̂ g p Ƃ Ȃ B Ȃ A CX900 ͂ 啿 炵 g p Ă ^ C I K ̃R N [ ( ̗֍s ) ɂ̓M M œ 傫 ł Ȃ L c B
͎ ͂ ア ̂ŁA x t T O X K v B Љ ł 悤 Ƀ N Ă ̂ɐ\ Ȃ A amazon ŋC y ɑI ŗ ŃT O X 킯 ł͂Ȃ B Ƃ ɂ͒n ̊ዾ ő k 悤 B
ʌ ͐ z s ߕ ( ̏Z ł Ƃ 납 炾 20km ) ɏZ ł l ́A J j ɑ k Ă݂悤 B X 傪 ] Ԃɏ l Ȃ̂Ŏ ̌ ɒ Ă Ă B ܂ A x t Ƃ Ƃ́A l i ͏ X 邪 œK ȃT O X Έ ̂ B
́A o S u x Ŏg p Ă āA V ݂̂Ȃ炸 A A A J Ȃǂ C ۏ ̉ ʼn K Ɏg p Ă B ̎ ɂ́A Ȃǂ ڂɓ 肻 Ȃ ̂ A Ȃ Ƃɂ͂Ȃ炸 A J ̘H ʂł͍~ Ă 鐅 ȊO ɗ Ԓ ł̑O Ԃ ̒ ˏグ Ȃǐ ł 邪 茩 Ėڂ K [ h Ă ꂽ B ԑ s O ɃN A I ̂Œ Ԃ͏ X ܂Ԃ C 邪 s R Ƃ͂Ȃ B K l Ńc [ O ɍs ƁA ڂ [ Ă Ƃ l ƁA ݎg p Ă T O X ł̖ڂւ̃_ [ W ̏ 悭 B ܂ A 2010 N 㔼 ł̓V N N X [ X ɏo 肵 킯 A Ԏ U ɂ A ] Ԃ S Œ 肵 Ă Y 邱 ƂȂ A E ɖ ܂ Ȃ B J j ̓X ̑O ͎ ] Ԃ u ₷ 悤 ɂȂ Ă 邼 I A J j ɓˌ 悤 B
̓n h o [ G h ɂ ^ C v g p Ă B 납 ڋ߂ 鎩 Ԃ A Ԃ g ł Ȃ ̐l t Ă Ă 邩 U Ԃ炸 Ɋm F ł X O m B
u x Ƀf W J ŎB e w ̃| P b g Ɨ Ƃ Ƃ u c u c Ă A ɋ Ă i B Ƀf W J Ă āA Ƃ ɂȂ T b Ǝ o ăp ` ƎB 鐡 @ B ɕ֗ Ȃ̂ŁA ~ j r㻂 ꂽ Ă B u x ̃L [ V [ g Ă āA Ńn @ n @ Ȃ \ o āA Ȃ C 킵 A ɕ֗ ȏ ꂾ B A U E J Ȃǂ̐ E / ቷ ɂ 炳 邱 Ƃ͊o 債 Ȃ Ƃ Ȃ B ̏ꍇ PENTAX h f W ^ J Optio W90 Ƃ J g p Ă ̂œ ɖ Ȃ A R g 悤 Ƃ ̓J ɂ Ĉ l ̗] n 낤 B
n h ɑO Ɠ ⋗ v GPS p [ [ ^ Ȃǂ Ă Ƃ ꏊ Ȃ Ȃ B Ńo [ ݒu āA t ꏊ 𑝂₷ 킯 B ̍ہA ȃ m ƐU ȂǂŐ܂ꂽ A Ȃ 肵 A R ̓K b ` t B g p Ă u ֗ z _ [ Q v ͂ d A y ē ̃K b ` 郂 m ߂ B
܂ A ̎ʐ^ ̂悤 ɑO Ɠ C g z _ [ ē _ ˂ 邱 ƂŌ 肷 B _ ˂ ƁA P O d r O { g 悤 Ȓ C g ł d S l ɖڂ ς O Ɏ t 邱 Ƃ \ B 肵 ƁA ͂ȃ C g ŁA ԑ s ɂ Ȃ Ǝv B
ق ̃ m ݂͂ ȍw ̂ A R ͎ ŕ i Đ 삵 ̂ B Ƃ Ă H 킯 ł͂Ȃ A2010 N BRM320 300km A ^ b N ̐V ̍ ڂ Ε Ƃ A J Đj ʂ B 悤 ȃ m Ă l Ƃ x ̂ŁA [ q g ߂ȃ m Ŏ Č Ăق B
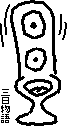
| i | V F A | |||
|---|---|---|---|---|
| L A o b O | e ʂʼn ł 肻 | TREK C ^ [ ` F W g N | | | 2011 N ͎ O Ă | ~ |
| g ̂ăJ C | C ƌC J o [ ̊Ԃɓ | ɂ͂ m K { | g p | |
| ւ | V c | Έ S | g p | |
| O | 60cm 炢 ƂĂ Z | 400km ȏ Ŏ Q 悤 | g p | |
| H | Y ͕K { ʓ E u h E } g f L X g Ă݂ | @ | g p |
L A o b O ͏ ̎ʐ^ ̗֍s ܂Ɏ ܂ Ȃ B ΗL p B Ƃɂ B L A Ƀ~ Q ֍s ܂ ł Ԃ牺 B
A ꂪ i B ܂艽 ł 邵 A ł ̂ d ʂ ŁA Ɍ ア ɂ͑ ςȂ ו ɂȂ Ă ܂ B InterMax ăL A o b O Ȃ Ă ǂ ɂ Ȃ 킯 ŁA \ l ƂȂ Ă 悩 B n 肾 ֗ Ȃ 肪 ȏ t Ȃ ł ǂ ɂ m b ق N ɂȂ Ǝv B A 펞 300W 炢 ł 悤 Ȃ Ă Ȃ A ꎞ ԘA ő o ͂ 200W x ̓ ɂ͏d ׂɂȂ Ă ܂ B č ͑ Ȃ ŃK o 낤 Ǝv B
C J o [ ƌC ̊Ԃɋ Ŏg p A ~ Ɏ ] Ԃ̑ s ̋ Ԃɂ 鈳 | I ȕ M ͎g ̂ăJ C ̔ M ʂ A ₽ Ȃ Ă ܂ B āA ҂ Ă 鎞 ԂɎg ̂ăJ C ̐ b ɂ͂Ȃ A ɂƂ Đ^ Ɏg p r Ƃ Ă̓~ ̑ s ̑ ̕ۉ Ƃ g ߂ɂ͎g Ȃ B ʂ Ȃ ̂ŁA ̃u x ɂ͕s v ̑ B R ŏ\ Ȑl n Y B c ȔM ʂ Ă ̂ɁA ɂ܂Ō ɏ M ʂ ^ Ă Ȃ ͎̂ Ɏc O A ̑̎ Ȃ̂Ŏ J Ԃ Ă B Ȃɂ 肪 狳 Ă B
O Ȃǂ Ă Ǝv A ͍ ʌ ɍݏZ ō ʌ o ̃u x ɂ o Ȃ ̂Ō ǂ͕s v ȑ B
͍ ̃^ C v ̊ Ȃ ̂ Q Ă d ̂ŁA E ̃^ C v Q 悤 ɂȂ B A ǂ̓u x ͎ ] Ԃ 痣 邱 Ƃ͂قƂ ǂȂ ̂ʼnE ̃^ C v s v Ƃ B N 600km ł Ă h Ȃ ő 葱 Ă ̂ł Ȃ Ƃ ł 킯 A ꂩ Q 悤 ǂ 悤 Y ށB 2011 N 400km ȏ Ȃ玝 Q Ǝv A 300km ȉ Ȃ玝 Q Ȃ Ǝv B
ʓ ͋z ꂽ 炷 ɃG l M [ ɂȂ Ƃ ƂŁA ɗn Ĉ ł݂ Ȃ ɂ Ȃ 艺 肵 ̂œ 퐶 ̊Ö ɂ g Ȃ Ƃɂ B A  à ̂ŗ ₷ َq ɂ͌ Ă Ǝv B
} g f L X g ͔ ɖ𗧂 Q ɂ͓ ̂Ńc [ O ɏo O A K s O ȂǂŁA V A ɐU 肩 āA ĐH ׂĂ B S Ȃ n K [ m b N ɂȂ ܂ł̎ Ԃ Ȃ 悤 ȋC B u x Ɏ Ă ɂ͂ ꂸ CP ₻ ȊO ̃R r j Ȃǂō ̓ ݕ ōς܂ ƂɋC Â B Ƃ A ͉ ł H ׂ 悤 ȋC B
̓` [ u ɓ Ă Ďg ₷ Ǝv ̂ A ӊO Ƃ n ߂ ܂ł̃n [ h ̂ŕs v Ǝv B
~ j r㻂͗L p Ǝv B A 10 { قǎ Q A 2-3 { Ώ\ Ǝv B ƐH ׂ₷ Ƃ Ƃ ŁA S ~ x ^ x ^ ɂ 邱 Ƃ _ Ǝv B
v Ƃ lj Ă݂ Ǝv B ӌ E z } B
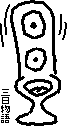
(SHIBATA Akira) , { T C g p ̍ۂɋN 邩 Ȃ s v ɑ , ؐӔC ܂ .